なんでもで早くできた娘が、21歳でまさかの自閉スペクトラム症(ASD)の診断。
思い描いていた未来とは違う道。
ゆっくり娘のペースで歩いていこうーーーそんな私たちの記録です。
この記事では、
・娘が21歳でASDと診断されるまでの背景
・母親としての戸惑いと気づき
・発達グレーな娘と家族の、3年がたった今の歩み
について、お話ししたいと思います。
同じように、我が子が大人になってから発達グレーだと気づいた親御さんや本人がこの記事を読んで、
「ああ、あの気持ちは自分だけじゃなかったんだ」
「誰も悪くない、こうやって生きていく道もあるんだ」
そう思ってもらえたら、嬉しいです。
幼少期〜中学受験:育てやすかった娘
私たち夫婦の第一子として生まれた娘。
妊娠がわかった時、娘が生まれた時、人生でこれほど嬉しいことがあったのかと思うくらい、それはそれは嬉しかった。
両家にとっても初孫だったので、4歳で弟が生まれるまで、ひとりっ子の娘は360度ぐるっと一周、どこに手を伸ばしても応えられ可愛がられて育ちました。
絵本が大好きで、言葉の理解も早く聞き分けが良かった娘は、幼少期から手がかかって悩んだという経験はなく、どちらかというと育てやすかったと思います。
そんな娘は、3歳には絵本から字を覚えて自分で書き始めたり、英会話のスピーチコンテストの全国大会に呼ばれたり、何をやっても私の予想を超えてよくできて、いつも私たちを喜ばせてくれました。
中学受験もそうでした。
チラシを見て、たまたま受けた塾の模擬試験で、国語の偏差値が80台後半というクリティカルヒット!
塾に通ったことのなかった娘が、そのままの流れで小学6年生の春から中学受験を始め、驚きの合格!!

『この子は、きっとどこまでもいく。
私たちの手から、どんどん離れていってもいい。
どこまでも遠くへ、自分で選んだ未来を掴んでいってほしい。
この子はきっと、どんな夢も手にいれることができる!』
私には、そんな確信さえありました。
未来に影がさした思春期のはじまり
突破した難関の国立中高一貫校。
初めこそ楽しそうに通っていたけれど、中学1年の3学期頃には友人と上手くいかなくなり始めました。
週末は遊びに行かず家にいて、いつも誰かが良くないという話をするように。
実は、小学4年生頃から、仲良しの友達がなかなかできなかった娘。
小学4年生といえば、親友とかグループとか、女子が女子らしく友人関係が変化する頃。
そんな周囲の変化に、娘は乗ることができませんでした。
学校の帰り道は、ポツンと一人で歩いていたり、お誕生日会に呼ばれても先にひとり帰ってきたり。
私は、積極的にうちにお友だちを招いたりしたけれど、娘のそんな姿は学年が上がるにつれてより顕著になりました。
母親として、娘の姿を見て胸がキューーーーッとなる日々を過ごしました。

「なんでだろう?みんなと娘は、一体何が違うんだろう?」
「このまま娘を置いておくよりも、優秀なら違う環境に行かせる方が娘にはいいのかもしれない」
このことが娘の中学受験を決めた、私自身の大きな理由でもありました。
娘にはいつも話しかけていました。
『あなたを待っている友だちがいるからね。大丈夫、大丈夫。』
振り返ると、そう娘に語りかけることで、自分自身にも言い聞かせていたのだと思います。
学校を休むことはなかったけれど、高等部に上がる頃には、ますます友人関係は狭く狭く、狭まっていたようです。
そして、学習面についてもこれまでのようにはいかず、徐々に苦労するようになっていました。
のちに数学面の学習障害を指摘された数学は、特に苦労しひどい状態なのに、幼少期に話していた獣医の夢をなんとなく親子で引きずり、切り替えることができずにいました。
さらに、高校1年生に発症した腎疾患により、高校3年間で合計4ヶ月以上入退院を繰り返すことになり、受験勉強もままならず。
進路を十分に話し合えないまま、大学受験を迎えた高校3年夏。
腎疾患が再燃したこともあり、最後の最後にやっと親子で話し合い、国公立は諦め私立文系へ進路変更。
受験科目が得意の英語と国語に限られ、ほっとしたあの子の顔を今でも覚えています。
次から次に何かが変わり、娘の生きづらさが見え始めた思春期。
でも私は、まだ確信した娘の未来にしがみついていました。
ASDの診断が下りた日、私が思ったこと
大学2年の冬。
娘は「聞き取り困難症(LiD/ASD)」の診断を受け、その診断の過程で、発達検査も行われました。
結果として、自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠陥・多動症(ADHD)の傾向があると指摘され、その後、精神科にて正式にASDの診断を受けました。
(※耳鼻科での発達検査に基づく指摘ではありましたが、当ブログではこの段階を「ASDの診断」と表記させていただきます)
あの時の気持ちは、今もわかりません。
ショック?
意外?
それともなんとなく予想していた?
でも、ひとつだけはっきりと感じたこと。それは、

「これまでのいろんな出来事が、すべてつながった気がする」
というのも、すでにこの頃には大学生活もうまくいかなくなっていました。
大学に合格した時、新しい環境で大好きな文学を存分に学びながら、のびのびと過ごすことができると思っていました。
同じ価値観の仲間と出会い、楽しい日々を送ってくれると信じていたのです。
でも、やっぱり同じでした。
同じ価値観とか、しがらみとか、性別とか、年代とか___そういうものではなかった。
「娘は人と上手く関われない」という現実を認めざるを得ませんでした。
診断によって、その理由がわかった気がしたのでした。
絶望でも、失望でもない。
そうなんだ・・・という感情?
そして___
腎臓病、LiD/APD、そしてASD。
次から次と、娘が背負うものがあまりにも多く、あまりにも大きいことが、ただただ可哀想になったのです。
それは、母親である私のせいかもしれない、私の育て方が間違えていたのかもしれない。そんな風に、自分を責める気持ちもありました。
全て、治ることはない。
一生付き合っていかないといけない。
それから3ヶ月後、大学3年の5月。
娘は「大学を休学する」と言い、話し合う間もなく休学届を提出しました。
ひとりで考え、気持ちを決めていた娘。
自分の気持ちを貫いたのは、あれが初めてだったかもしれません。
そうして、娘は一旦社会から距離を置くことを選び、私たち家族もまた、「発達障害」という言葉と向き合う時間が始まったのです。
発達検査、診断に意味はあるのかな?母としての感情と現実
ASDの診断を受けた後、私は本を読みネットで調べ、職場の心理士にも相談しました。
『発達障害』『ASD』『特性』『問題行動』____
情報と知識でパンパンになった私の頭は、娘の言動を「こだわり」「パニック」「過集中」など、ASDの特性を軸にしてカテゴリーに分けて、考えるようになっていました。
そのほうが分かりやすく、「こうすればいいんだ」「こんな風に考えればいいんだ」と、娘をなんとかできるように思えたんだと思います。
それに、「ASDだから仕方ない」と思うことで、自分が少し楽になりたかったのかもしれません。
でも、気づけば娘の気持ちに目を向けることが減り、娘との距離もどこか広がったように感じました。

「理解しようとすればするほど、娘が離れていく」
日常の困りごとはどんどん大きくなり、娘との関係もギクシャクして、いよいよ家の中だけでは抱えきれなくなり心療内科に通うことになりました。
そこから1年___
娘だけではなく、主人と私も家族カウンセリングを受け、ようやく少しづつ見え方が変わってきたように思います。
今では、ASDの特性に当てはめて考えることもあるけれど、それが”娘そのもの”とは思わなくなりました。
検査結果や診断は、たしかに一つの「わかりやすさ」かもしれません。
けれど、それが「正解」や「全て」ではないということも、少しづつわかってきた気がします。
私は一時期、

「娘がASDになっていっている気がする」
と、悩んだ時期がありました。
その思いを職場の心理士に相談したら、
「だってASDなんだもん!」
と笑われて、すごくショックを受けました。
自分でも矛盾していると思います。
診断に頼り、”カテゴリー”に当てはめることで娘を理解しようとしていたのに、気持ちの奥では娘を”カテゴリー”に当てはめて、片付けることに抵抗があったんだろうと思います。
もちろん今も、娘の嗜好や思考にASDの特性を当てはめることがないわけではない。
でも、「だからASDだ」と、娘を決めつけるような気持ちははなくなりました。
耳鼻科の先生が、以前、私たちに言ってくれた言葉があります。
医師:「発達障害って、診断じゃなくて、傾向を知るためのものなんだよ。だから”スペクトラム”っていうんだね。これから大切なことはその特性を知って、どう付き合っていくか。診断に囚われないでどう生きていくか、それが大事なんだよ。」
この言葉に、私は救われました。
困りごとがあっても、なんとか社会でやっていけている娘のような、いわゆる”発達グレー”の人にとって、診断はすべてじゃない。
検査や診断は、時に必要で、うまく使えば助けになるけど、使い方を間違えれば、むしろ逆効果になる。
つまりは___「取り扱い注意⚠️」ということですね 笑
あれから3年がたった今。まだ途中だけど、わたしたちらしく
ASDの診断から、3年が過ぎました。
振り返れば、本当に色々あって、私にとっては
「あんなに色々あったのに、まだ3年?!こんなに変わったのに、まだ3年?!」
という感じです。
お金のこと、バイトのこと、大学復学のこと、きょうだいのこと、家族のこと、そして、娘と私自身の関係のこと。
社会の中で生きていくというのは、幾つもの難問を同時に解いていくようなもの___。

「不安しかない」
と話しながらも、娘なりに考え、これからの就職や働き方を見据えて、この春から大学院進学を選んだ娘。
医師や心理士さんだけではなく、大学の学生支援課の担当の方、信頼する教授、SNSで知り合った趣味が共通の仲間に支えられ、少しづつゆっくりだけど、確かに進み始めています。
私も周囲の人に支えられながら、娘との向き合い方が少し変わってきました。
そのおかげで、以前よりずっと穏やかな日々を過ごすことができています。
「やり直せるなら・・・」と過去を思う気持ちはあるけれど、休学に関してだけは娘の決意を尊重して良かったと、あの時の自分を振り返ります。
娘の気持ちを無視して、せめて前期だけでもと通わせていたら___
今、娘はいなくなっていたかもしれない。
あるいは、娘らしさを失ってしまっていたかもしれない。
あの頃、家の中が娘の世界の全てだったときに私が感じた”確信”は、今も形を変えながら心の中にあって、私を支えてくれている。
娘との日々を幸せだと思う。
まだまだ、道の途中。
これまでの出来事、嬉しかったことも、苦しかったことも後悔も、すべてをここに記していくことで、これからも先に続く娘と家族の未来に繋がっていくと信じている。
そして、もしもこの記録が、似たような立場で悩んだり、迷ったりしている誰かの小さな励ましや安心になれたら。
それ以上に嬉しいことはありません。

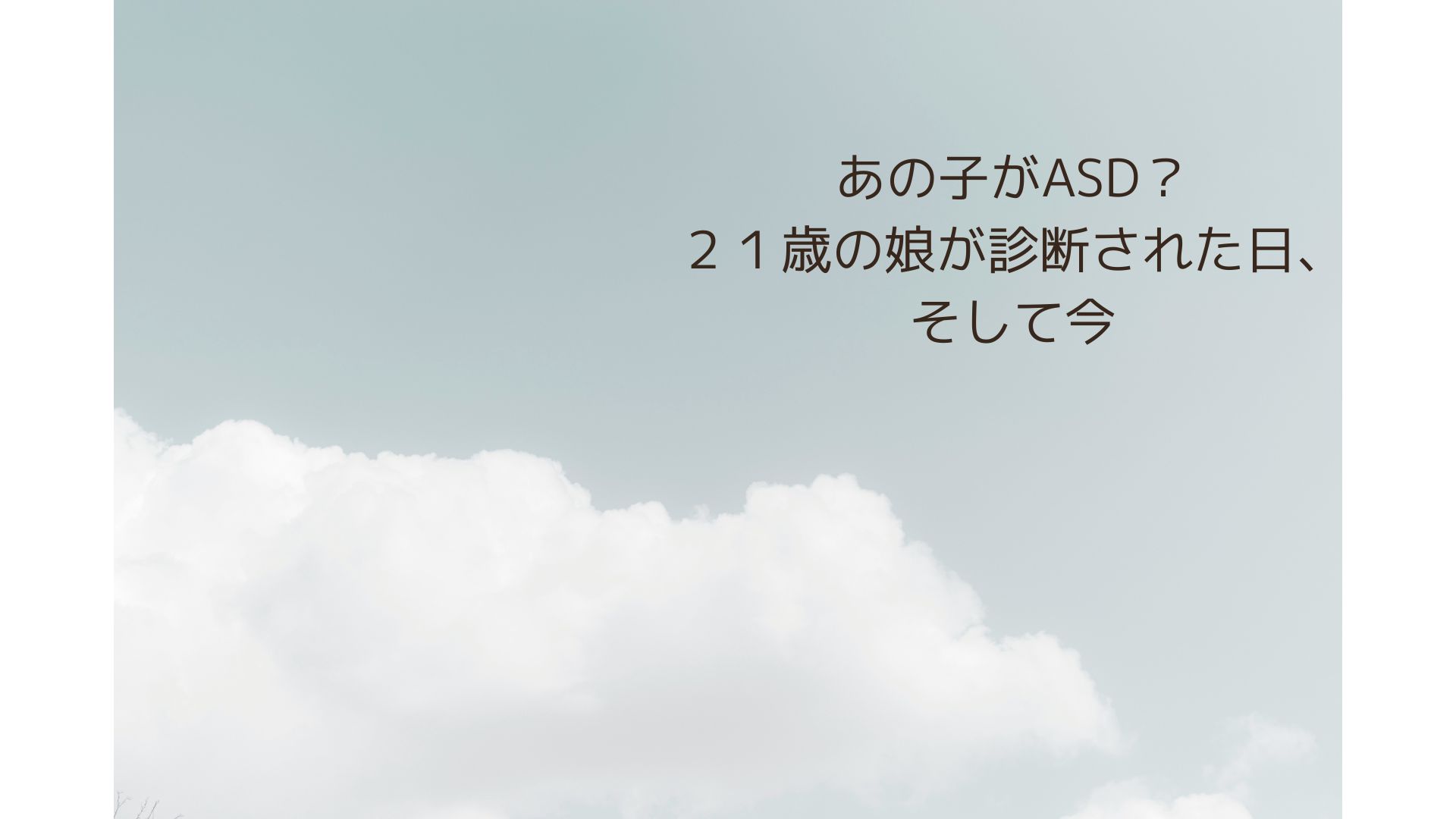
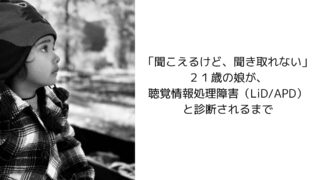


コメント