娘が「聞こえているのに、何を言っているのか分からない」と訴えたのは、あるアルバイトの初日のことでした。
そのときはまだ、「聞き返すのが苦手なのかな」くらいに思っていましたが、そこから少しずつ、娘が抱えている見えにくい困りごとに気づいていくことになります。
この記事では、娘が「聴覚情報処理障害(APD/LiD)」と診断されるまでの経緯、診断後に始めた日常での工夫、そして現在受けている支援について、母親としての視点からまとめてみました。
同じように「聞こえにくさ」に悩む方や、その家族の方の参考になれば幸いです。
診断に至るきっかけ
気づいたのは、娘が21歳の時。 きっかけは飲食店のバイト初日、混雑した厨房で、周囲の音が混線して会話がわからなかった経験をしたことでした。
詳しく話を聞くと、

・話しかけられる声と、周りのお客さんの話し声、お皿がガチャガチャいう音が同じ大きさになって、話しかけられてる内容が聞き取れなかった。
・今までも同じように『聞こえているのに、聞き取れない』ことがあった。そういえば、学校のグループ学習とか、いつも困っていた。
すぐに耳鼻科を受診しましたが、聴力検査の結果は異常なし。
聞こえにくくなる状況を医師に説明しましたが理解してもらえず、聴力検査では高音・低音どちらの領域でも問題のない値を示すため、経過観察として帰されました。
何が何だかわかりませんでしたが、振り返ると高校1年、2年の校内の健康診断で聴力検査の結果を「再検査」で持ち帰り、同じように検査をしてもその結果に異常は見られず、思春期のストレスでは?と経過観察になったことを思い出しました。
それも、繋がりがあるのかな?と、何もわからないまま相談した職場の心理士が教えてくれたのは「聴覚情報処理障害(APD/LiD)」でした。
🔍 聴覚情報処理障害(APD)とは?仕組みと特性
APDの定義
**APD(聴覚情報処理障害/Auditory Processing Disorder)**とは、耳では音がちゃんと聞こえていても、脳がその情報をうまく整理できずに、言葉として理解するのが難しいという障害です。
特に、次のような特徴があります:
(=カクテルパーティー効果がうまく働かない)
聞いた内容をすぐに忘れてしまう (=聴覚ワーキングメモリが弱い)
似た音を区別しづらい(例:「さ」と「た」など)
一度に複数の指示を理解・処理するのが苦手
一般的な聴力検査では異常が出ないため、聴力には問題ないと判断され、本人の努力不足や性格のせいと誤解されやすいのも、この障害のつらい点です。
また現在、APD/LiD(Listening Difficulty)には確立された治療法はなく、脳の“特性”や“偏り”によるものであると考えられています。
🔍 APD(聴覚情報処理障害)の診断までの流れ
聞こえているのに分からない
聴力は正常
WISC等の発達検査
ASD(自閉スペクトラム症)/APD(聴覚情報処理障害)
※あくまで一例で、地域や医療機関によって多少異なります。
🌱 はじまりは「聞こえているのに、わからない」という違和感
【日常生活の中での“なんとなくの困りごと”】
- 会話の内容が頭に入ってこない
- 特定の環境(雑音の多い場所など)で聞き取りにくい
- 騒がしい場所で人の話を聞き取るのが苦手
- 背後から呼びかけられると気づきにくい
➡️ でも、聴力検査では「異常なし」と言われることも多く、「気のせい」「集中力の問題」と見過ごされがちです。
【発達外来や耳鼻科への相談】
「聴こえには問題ないのに、会話が理解できない」という状態を相談するために、まずは以下の診療科へ。
- 耳鼻科(とくに補聴器外来や言語聴覚士がいる病院)
- 発達外来、小児神経科、心療内科
➡️ 娘の場合は、一般の耳鼻科外来を経由して専門の聴覚検査を受けることになりました。
【聴覚情報処理の検査(APD検査)】
専門の医療機関で、言語聴覚士(ST)が行う検査を受けます。 これは“聞こえている音をどう処理しているか”を調べる検査で、内容はこんな感じです
- 雑音の中で言葉を聞き取るテスト
- 左右の耳に違う音を聞かせるテスト(ディコティックリスニングなど)
- 音の順番や高さを聞き分けるテスト
⏱ 検査時間はだいたい1~2時間。本人の状態によっては2回に分けることもあります。
【医師のすすめで、発達検査を受けることに】
聴覚情報処理検査の結果をふまえて、医師から「APDの背景に発達特性が関係している可能性もある」との指摘があり、発達検査を勧められました。
APD単独の診断でも支援は可能ですが、発達特性(ASDやADHDなど)を併せ持つ場合には、支援の方向性や支援機器の使い方が異なることもあるためです。
➡️ 娘もこのタイミングで、初めて発達検査を受けることになりました。
こちらの記事もぜひご覧ください。
【医師による診断と説明】
検査結果をふまえ、医師が「APD」の診断を出すかどうかを判断します。
娘の場合は、検査の所見と、日常生活での困りごとを丁寧に照らし合わせて
「聴覚情報処理に弱さがあるため、雑音下での聞き取りが著しく困難」という診断になりました。
また、発達検査の結果からASD(自閉スペクトラム症)の特性もみられることがわかり、「聞こえてはいるのに、理解しづらい」背景には、APDとASDの重なりがあると説明を受けました。
📝 PDFはこちら → https://apd.amed365.jp/doc/202403-seika.pdf
🧩 なぜAPDの診断に発達検査が必要なの?
APDの診断は、聴力に問題がないことを前提に、脳での音の処理に困難があるかを調べるものですが、その評価には以下が求められます。
| 必要な要素 | 理由 |
|---|---|
| 発達検査(WISCやWAISなど) | 知的な発達水準とのバランスを見るため。聴覚情報の処理だけが極端に低い場合、APDの可能性が浮かび上がります。 |
| 言語理解・作動記憶などの検査 | 音の記憶、聞いた情報の保持・処理能力を見るため。 |
| ASDなど他の発達特性の評価 | 聴覚処理の困難さが、ASDの「感覚過敏」や「注意の向け方の特性」によるものかを見極めるため。 |
🧠発達検査(WAIS)の検査結果から、娘の脳に見られる特性
【作業記憶と注意の働き】
たとえば娘は、発達検査で作業記憶(ワーキングメモリ)の値が低いと診断されました。
これは、「聞いた情報を一時的にとどめて、意味を理解し、必要なことだけを残す」という脳の働きです。
この働きが弱いことで、娘には次のような様子が見られます:
- 長い話の内容を最後まで覚えていられない
- 複数の作業を同時にこなすのが苦手
- 忘れ物が多い
【カクテルパーティー効果が働きにくい】
もうひとつ、カクテルパーティー効果という、脳の“音の選び分け”の機能があります。
これはたとえば、にぎやかなパーティー会場でも、自分の名前や関心のある話題には自然と気づけるという脳のしくみです(=選択的注意とも言います)。
でも娘は、
- ざわざわした場所で呼びかけられても気づかない
- バイト先のケーキ屋さんで、カウンター越しのお客さんの声が聞き取れない
といった困りごとを抱えています。
☝️「障害」というより「聴こえの特性」と捉えたい
こうした症状は、耳そのものの問題ではなく、**「脳の中で音がどう扱われるか」**という仕組みの中で起きています。
だから私は、「APDは“聴こえ方の個性”とも言えるのでは」と感じています。
とはいえ、治療法がないからこそ、学校生活や社会での生活をスムーズにするための工夫がとても大切になります。
次の章では、娘と一緒に取り組んできた支援や工夫についてお話ししていきます。
🔍 日常での工夫・ツール活用
娘の普段の生活や学校生活での、工夫や活用しているツールをご紹介します。
📓メモ術「ノートにメモをとる」
「なんだ、メモか」と思われるかもしれませんが、娘には必須事項、ノートはアイテム。
ワーキングメモリの数値が低い娘は、
☆同時進行の作業
☆素早く情報を整理する
☆瞬時に優先順位をつける
ということが苦手です。
このことへの対策がメモを取ること。
まず、聞いたこと、見たこと、頼まれたこと、時間や場所など、忘れてはいけないことを全てとりあえずメモを取る。 そして、落ち着いたら、そのメモを整理し、頭の中も整理する。
どんどん流れてくる情報や会話をメモに残すことで、忘れることを予防しています。
使用しているのは、一般的な筆記用具とノート、そしてiPhoneのメモ機能。 ケースに応じて使い分けています。
でも、娘は診断される以前、中学生の頃から、どんなこともとりあえず、メモを取ってきたそうです。
無意識の行動ですね。
そして、現在。 用途に応じてノートを区別したり、常にメモを携帯し残すようにし、残した内容のまとめ方もマイルールを作って整理しているそうです。
📱デジタルツール活用
iPhoneのリマインダー、TODOリスト、アラームは常に働かせています。
ノートに記録しても、その日、その時間を忘れてしまうことも。
買い物や授業の課題の提出、待ち合わせ時間と場所、乗る電車など日々の「忘れてはいけない」ことに気づくためにリマインダーやアラームを設定しています。
こまめに記録、設定して、終わったら消す、という作業を繰り返しています。
Todoリストに関しては、ひとつづつ消えていくのが達成感が得られるようで、楽しんで使っています。
⏺️ICレコーダー
ICレコーダーは、大学の講義で、大学2年の後期が始まるころに使い始めました。
音が広がりやすい大講堂や、教授の話し方によっては講義内容が聞き取りにくい。
環境や状況により聞き取りにくさは様々で、聞き取りと理解の両側面から長時間の講義内容のメモを取ることは、かなりの集中力が必要のようです。
手書きのメモとICレコーダーの併用により、聞き漏らしのストレスはずいぶん軽減できています。
※授業中のICレコーダーの使用は、大学に申請し許可を得ています。 使用する場面により、必要な手続きなどがあると思いますので、確認と自己責任の上の使用が必要です。
📝 PDFはこちら → https://apd.amed365.jp/doc/202403-seika.pdf
🔍 補聴援助システム「ロジャー」と耳栓
🎧娘が現在使用している「聴こえ支援ツール」
娘が現在、聴覚のサポートに使用しているツールは、以下の2つです。
どちらもそれぞれに特性があり、場面によって使い分けています。 特にロジャーは、医師の紹介により、令和4年12月に導入しました。
一覧にまとめましたので、ご覧ください。
| 項目 | PHONAK ロジャーフォーカスⅡ・セレクト | KINGJIM デジタル耳栓 MM3000 |
|---|---|---|
| メーカー | PHONAK(フォナック) | KINGJIM(キングジム) |
| 構成 | 受信機(耳に装着)+送信機(卓上or話者が装着) | ワイヤレスイヤホン型(単体使用) |
| 装着イメージ |
補聴器型。髪の毛で隠れる場合あり

|
ころんと丸いイヤホン型。やや大きめ
|
| 機能 | 話者の声を背景音より大きく自動調整 | ノイズキャンセリングで環境音を軽減 |
| 聞こえ方 | マイクを向けた方向の声がクリアに聞こえるが、環境音も拾う | 雑音はほぼカット。人の声は小さめだが聞こえる |
| 向いている場面 | 授業・映画館・接客など、特定の話者の声を集中して聴きたい時 | 電車・図書館・自宅など静かな環境で過ごす時 |
| 主なメリット | 距離があっても話者の声が明瞭に届く | 環境音が大きくカットされ、静けさを保てる |
| 主なデメリット | マイクが向いていないと声が拾えない | 人の声も小さめで、特定の声だけ拾うのは難しい |
| 使用時の感想 | 「聞こえるけど集中が必要。援助ツールという実感あり」 | 「環境音がかなり軽減。聴覚過敏の人におすすめ」 |
| 備考 | 医師の紹介で購入 | 販売終了モデル(体験談として掲載) |
※情報は2025年6月時点のものであり、最新情報はメーカーHPをご確認ください。
🌐 メーカーHPはこちら → https://www.phonak.com/ja-jp
✍️実際の娘の使用した感想

ロジャー:
「聞くべき声がはっきりするけれど、
集中しないとやっぱり聞き逃してしまう」
「ロジャーセレクト(集音器)をテーブルに
置いて使用すると、グループワークの時など
聞き取りが楽になる。」
MM3000:
「耳栓だから、雑音も含めて全体の音が小さくなる。」
「iPoneとの連携がないから、本当に音をシャット
ダウンできる。満員電車など、混雑時の使用に
とてもいい」
「環境音が軽減されて楽になる。APDというより、
聴覚過敏の人に向いているんじゃないかな」
✍️実際の使用での聞こえの違い例
授業中、手元からペンを落とした時:

- ロジャー:
「教授の声も「カチャーン!」という金属音も、
どちらもクリアに聞こえる(音が響きすぎてつらいことも)」 - MM3000:
「教授の声は聞こえるけど、ペンの音はほとんど聞こえない。」
機器の特性により、適する場面は違うようです。
そして、万能でもない。 使用には、本人の工夫と経験が必要のようです。
こちらの記事もぜひお読みください。
次に、各ツールの企業HPや購入サイトの紹介です。
🧺娘が使っている&検討した「聴覚サポート製品」一覧
以下は、娘が現在使用しているもの・過去に使用したもの・医師の紹介があった製品・代替候補までを一覧にした表です。楽天・Amazonのリンクも併記しています(2025年6月時点)。
※一部製品は販売終了や医療機関を通じた入手が必要な場合があります。詳細は各リンク先をご確認ください。
| 分類 | 製品名 | 特徴・用途 | 楽天リンク | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ✅現在使用中 | PHONAK ロジャー フォーカスⅡ | 医師紹介で導入。授業・映画など話者の声を明瞭に聴きたい場面で活躍 | 楽天で見る | ― |
| ✅現在使用中 (販売終了) |
KINGJIM デジタル耳栓 MM3000 | 環境音を大幅カット。静かな場面や電車内などで有効 | 販売終了(掲載省略) | ― |
| ✅現在使用中 | PHONAK ロジャーセレクト3 | 話者の音声に集中できる送信マイク。教育・職場に | 楽天で見る | ― |
| 🔄現行モデル | PHONAK ロジャーオン 3 | 雑音に強くマイク自動調整。学校・職場・オンライン会議向き | 楽天で見る | 企業HP |
| 🪫消耗品 | ロジャーフォーカスⅡ専用 電池 | 定期交換が必要。使い方により異なる | 楽天で見る | ― |
| 🔍代替候補 | Apple AirPods Pro 2 | ノイズキャンセリング機能で音のストレスを軽減。iPhoneユーザー向き | 楽天で見る | Amazonで見る |
| 🔍代替候補 | SONY Link Buds Fit | 周囲の音を取り込みつつ、軽量で耳に負担が少ない | 楽天で見る | Amazonで見る |
| 🔍代替候補 | Anker Soundcore Liberty 5 | 比較的リーズナブルで、ノイキャン性能も高評価 | 楽天で見る | Amazonで見る |
💡読者の方へ】娘の使用体験談としてのご紹介です
今回ご紹介した聴こえ支援ツールは、娘が実際に使用した機種・使い方に基づく体験談です。
娘は「APD(聴覚情報処理障害)」と診断され、補聴器とは異なる支援が必要なタイプの聴こえの困難を持っています。
ロジャーやデジタル耳栓などの機器は、聴覚過敏や選択的注意の困難に悩む方にも役立つ場合がありますが、効果には個人差があるため、必ず専門家と相談した上での導入をご検討ください。
🔎 APD(聴覚情報処理障害)に関する社会的な支援について
現時点(2025年6月)では、「APD単独」で受けられる法的な支援や制度(障害者手帳や補助金など)はありません。
ただし、周囲の理解や「合理的配慮」によって、生活や学習の場面で支援が受けられるケースがあります。
支援の多くは「周囲の配慮」が前提です
APDは見えにくく気づかれにくい困難さのため、
支援の多くは「本人が状況を説明し、それを周囲が理解・配慮してくれるかどうか」が鍵になります。
- 授業での文字情報の補足(板書、スライドなど)
- 聴き取りやすい席への配慮
- 支援機器(例:ロジャーなど)の使用許可
- 聞き返し・メモ・筆談などへの理解
➡️ 医師の診断書があると、学校や職場での相談がしやすくなることがあります。
他の診断(例:発達障害)がある場合は、制度の対象になることも
APD以外に「自閉スペクトラム症(ASD)」などの診断がある場合は、
以下のような支援制度にアクセスできる可能性もあります。
- 発達障害者支援センターでの相談や支援
- 精神障害者保健福祉手帳の取得
- 自立支援医療(通院医療費の助成)
- 就労支援サービス(就労移行など)
就学・就労場面でのサポート
本人が困りごとを伝えられるようになることで、進学先・職場で配慮を得られるケースがあります。
- 学校:学生支援室や教員による個別対応
- 職場:障害者雇用や配慮申請、福祉機器使用の申請
もし支援について相談したいときは…
- 学校の「学生支援室」や「相談室」
- 地域の「発達障害者支援センター」
- かかりつけの医師や心理士
へ一度相談してみることをおすすめします。
おわりに:診断は「自分を説明するための道具」に
娘がAPDと診断されて3年が経ちました。
娘の大学は、幸運にも支援体制が充実しています。
授業中のロジャーの使用許可はもちろんですが、学内には学生ボランティアでノートテイカーが常駐しており、申請すれば一緒に授業を受けてくれます。
文字起こしアプリ(UDトーク)がインストールされたpadの貸し出しと授業での使用許可を申請できたり、その学生に応じた機器のサポートもあります。
また、娘の相談がきっかけで、ロジャーの貸し出しも始まりました。
NHKでこの障害が取り上げられたことをきっかけに、これまで気づかれにくかった「聴覚情報処理障害(APD)」が、少しづつ広がってきているように感じます。
それでも現実は、場面や体調によりロジャーや耳栓の支援機器が十分に効果を発揮しないこともあります。
娘の場合は、体調や気圧、ホルモンバランスにより聞こえ方も変化することもあります。
だからこそ大切なことは、「どう付き合っていくか」「どう困りごとをコントロールしていくか」。
支援機器だけに頼るのではなく、自分の状態に気づき、自分に必要な支援を選び取る力が必要になります。
診断をきっかけに、娘は「なぜつらかったのか」「どうすれば少し楽になるか」を、自分の言葉で表現できるようになってきました。
それは私たち家族にとっても、これまで見落としていたことに気づく大きなきっかけとなりました。
その気づきは、きっとこれから娘が自分らしく生きていくうえで、支えとなっていくはずです。
受診できる医療機関や支援制度はまだ限られていますが、同じような困りごとを抱える方々やそのご家族、まわりの方たちにとって、少しでも理解のきっかけになればうれしく思います。
📰 記事はこちら → https://www3.nhk.or.jp/news/special/lifechat/post_34.html

📚 娘の主治医が書かれた本のご紹介
APDについて、理解を深めるきっかけになった一冊です。
何度も読み返すたびに、「聞こえているのに聞き取れない」とはどういうことかを知りました。
当事者・家族・支援者、すべての方におすすめしたい本です。
マンガでわかるAPD 聴覚情報処理障害阪本浩一 著
娘の主治医が書かれた一冊です。
APDについての理解を深める、大きな手助けとなりました。
ご家族や支援者の方にもぜひ読んでいただきたい本です。

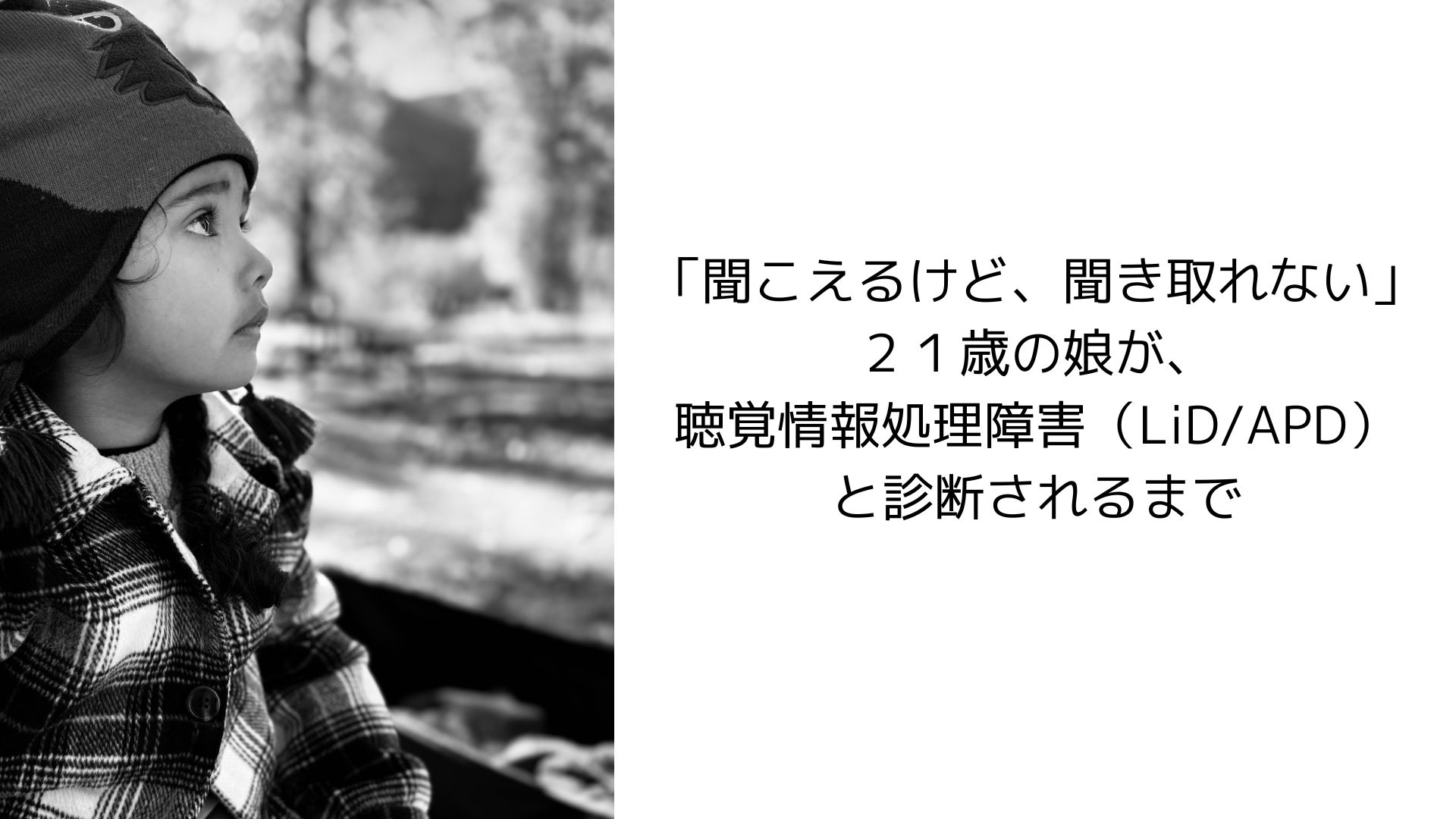
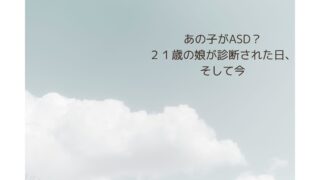


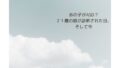

コメント