まず初めに、「メンタル」「カウンセリング」と聞いて、どんな印象がありますか?
私も娘がメンタルクリニックの受診とカウンセリングに通い始めるまで、ネガティブな印象を持っていました。
でも、通院から1年。
その印象は大きく変わりました。
娘は、信頼するカウンセラーさんに支えられ、少しずつですが娘らしく進みはじめています。
心理的カウンセリングについて、私のスタートライン、印象の変化、カウンセリングの実際、そして娘の現在について、カウンセリング受診について現状のデータも踏まえてお話しします。
☆最後に、お勧めのオンラインカウンセリングサイト「kimochi」をご紹介しています。
よかったら、参考になさってください。
▶ オンラインカウンセリング[kimochi]
心理的カウンセリングについて
心理的カウンセリングとは
心理的カウンセリングとは、公認心理士やその他、心のサポートに関する有資格者(カウンセラー)と対話しながら、心の悩みやストレスなどの心理的サポートを受けることを指します。
特に、日本における国家資格として定められている「公認心理士」は、公認心理士法に「国民の心の毛脳の保持増進に寄与すること」を目的として、心理的支援や相談、助言、教育などを専門的に行うことができるとされています。
カウンセリングを受けられる場所は、精神科やメンタルクリニック、心療内科などの医療機関、また独立した「カウンセリングルーム」「相談室」などのカウンセリング専門の施設もあります。
最近では、「オンラインカウンセリング」など、SNS上でも相談ができるなど、さまざまな工夫がされていて、自分に合った場所を探しやすくなっています。
私のスタート地点|心理的影響と受診の実際
メンタルクリニック、精神科、心療内科、心理的カウンセリング。
通院前、私にはあまりいい印象はなかった。
・気持ちなんて、自分でなんとかできる
・まだ必要ない
・知り合いに(通院を)知られたらカッコ悪い
・頼り切ってしまいそう
・後戻りできなくなりそう
こんな心理的抵抗が強かったのです。
この思いや抵抗感は、
私が看護師の専門職だから?
ASDの娘を持つ家族だから?
私が、ど根性で育った昭和人間だから?
そんな風にも思っていましたが、調べてみると、年代、性別を問わず日本人のスタンダートな意識のよう。
また、こちらの2つのデータでは、その心理的抵抗から実際の受診が影響を受けていることが浮き彫りになっています。
現状データから見える心理的抵抗
▶ カウンセリングの現状|中小機構J-Net21利用率のギャップと課題感
▶ カウンセリング意識調査(PR TIMES)これらのデータからは、
☆重要性、関心がある53%にも関わらず、実際の受診に対する心理的抵抗を56.5%が抱えている。
☆そして、カウンセリングの必要性を55%が感じているが、実際の利用は2021年の調査では13.4%に留まっている。
☆しかし、仕事やパフォーマンスに47%の人が影響を感じている。
ということなどが、読み取れます。
| 項目 | 数字/割合(日本) | 傾向・背景 |
|---|---|---|
| 悩み・ストレスを感じている | 約70〜93% | 世代や調査対象によりばらつきあり |
| カウンセリングに対し重要/関心あり | 約53〜55% | 多くが必要性を感じている。特に20〜30代で多い |
| 関心があるが、心理的抵抗がある | 約48〜57% | 心理面、費用面、時間、信頼性において抵抗がある |
| 悩み・ストレスを感じている | 約70〜93% | 世代や調査対象によりばらつきあり |
| メンタルの不調による影響を感じている | 約47% | 熱意、集中力、生産性の低下を感じる人が44.1% |
| 実際に利用した | 約13%(2021調査) | 利用全般の受診に対するハードルが高く、※OECD平均(10〜15%)と比べても低水準 |
※OECD(経済協力開発機構)とは、先進国を中心に、経済成長、貿易の自由化、開発援助などを目的とする国際機関のこと
心理的抵抗の背景|ザ.日本人
| 調査データから見える傾向 | 全体的な割合 |
|---|---|
| 「自分には必要ない」 | 53.7% |
| 「自分を弱いと思われたくない」「精神的偏見」 | 56.5% |
| 「メリットが分からない」「効果がないと思う」 | 31.5%、17.6% |
| 「信用性の不安」「どこで誰に相談すればわからない」 | 38.2% |
私の場合、信頼性についてのネガティブな印象の理由を言葉にするなら「心や気持ちは形にならないものだから」。
形にならないものを扱うためには、その人(たとえば医師、カウンセラー)が形として捉え、該当するフォルダに分類し、理解という言葉に置き換えるしかないのでは?と思っていた。
そして、分類、整理がどうにもできなければ投薬に頼ることになる、と。
看護師の私でさえ、そんな印象、思いがあった。
私だけではなく、多くの人が抱くこれらの心理的抵抗の背景はなんだろう?
やはり、日本らしさという文化的な背後構造が影響している?
たとえば、恥の意識や劣等感などがあるかもしれません。
また、偏見を持っていると、どんなことであっても避けて通ろうとするのが、人間の性。しかし、避ければ正確な情報は得られない。必然、情報不足となり、心理的影響につながる大きな要因になります。
そんないくつかの要因が、複合的に組み合わさって現れているのではないかな。
カウンセリングが生活の一部である欧米との大きな違いです。
私たちの変化|カウンセリングの実際
「まだ必要ない」「後戻りできないかも」「他人がどうにかできるの?」と、受診にネガティブな印象であった娘と私が、なぜ受診することになり、どう変化したのか。
受診を決めた理由
結論を先に言うと、考える間もなく必要に迫られた結果、と言うことになる。
あの時、2回目の娘のお金の問題が発覚した。
この件で、娘への信頼が全くなくなった。
親子を、家族をやり直すことに対して、娘だけでなく自分にさえ自信がなくなった。
だから、他の手を借りるしかないと思った。
もう考える余地はなかった。
迷わず、自宅近くの出来たばかりのメンタルクリニックの通院を決めた。
でも、もし、あの時まだ考える余裕があったら、未だ受診せず、娘と家族の状況はもっと悪化していたかもしれない。
「家族カウンセリング」のスタート
初診の当日から、娘とは別室で同じカウンセラーさんによる、私たち夫婦へのカウンセリングが始まった。
数ヶ月間は、2〜3回/月のペースで診察とカウンセリングがあったので、私たちはその度に取り留めなく話した。
カウンセラーさんは、特にアドバイスをすることもなく、うなづいて話を聞かれていた。
実際、その頃にカウンセリングの効果を感じたかというと、そうでもなかった。
娘に対する不信感は消えることはないし、娘の態度が変わるわけでもなかった。
相変わらずの緊張状態。
それでも一緒に通院して、順番にカウンセリングを受けることを続け、半年ほどが経過した頃。
どんなに必要なことであっても「嫌は嫌」で拒否してしまう(そんなことは意思表示できる💢)娘が、このメンタルクリニックには欠かさず通院することに、私のカウンセラーに対する信頼が強くなり、任せておこうと思えるようになり、娘一人で通院するようになった。
以降は、必要時に電話で相談の形のカウンセリングをしていただき、変わらず私も支えてもらっている。
ここまでの積み重ねには時間がかかった。
でも、今の安心はその「効果を感じていなかった」時間のおかげだと思っている。
娘が話し始めるまで
気持ちの表出が苦手な娘。
だから、対人関係でストレスを抱えやすく、私から見ると簡単に解決できそうなことも解決できず、またストレスになる。
自分の中で問題が大きいと感じれば感じるほど、私にも誰にも話さなくなる。
カウンセリング当初、娘は泣いてばかりいたと、最近聞きました。
30分間、泣いて何も話さず終わることも少なくなかったと。
私たちの30分間との違いに、今更ながら胸が痛む。
でも、娘もその時間を超え、今は自分の思い、考え、考える方向性、迷いを話すようになり、次第に筋道や理論立てができるようになってきた、ということも教えてくれました。
娘と家族・1年後の今
1年間を経験し、カウンセリングに対し、私の知識不足と偏見が大きかったことを感じます。
カウンセラーさんが、どんな手技、手法で娘と私たち家族を解きほぐしてくれているかは分からない。
でも、あの時、102回目にやっと繋がった予約の電話。
娘と同世代以下の親子連れでいつもいっぱいの待合室。
私の職場で、脱落していく若いスタッフ。
そんな現実を眺めながら、心の支援の需要について考える。
娘と家族は、メンタルクリニックの医師やカウンセラーカウンセラーを信用している。
だからと言って、頼り切っているわけでもない。
娘の今の姿は、1年前には想像できなかった。
自立に向けて、人に比べてゆっくりで遠回りで、凸凹が多いかもしれないけど、でも、それが娘のペースとして、支えを受けながらゆっくりゆっくり進んでいる。
娘が、メンタルクリニックを受診して、カウンセリングを受け始めてよかったと思う。
だから、誰もが難しいことを考えず、熱が出たら受診するように、心のしんどさの受診やサポートを求めることが当たり前になればいいな、と心から思います。
この記事が、娘の体験が、娘のようなASDなどの発達障害での困り感だけでなく、気持ちのしんどさを抱え、通院やカウンセリングに迷っている方々の後押しになれば幸いです。
👀おまけ
カウンセリングをどこで受けるか?
私見ですが、安心してカウンセリングを受けるためには、同時に医師の診察も必要かな、と思います。
それは、やみくもに心に向き合うばかりではなく、そのしんどさの根本原因を知ることが必要で大切だから。
たとえば、娘は自閉スペクトラム症/ASDの診断を受けています。
診断を受けたからこそ傾向を知り、生じがちな問題や抱える課題をある程度予測し、理解できる。
そしてその前提は、今抱えているしんどさに繋がり、本人の生育の背景や家族との関わり、また家族の背景も含めたカウンセリングへと発展していくことが、娘の経験から有効だと思うから。
特性によるものであれば、本人のせいではないと考えることや、ある程度「仕方ないよね」と、割り切ることもできる。
また、周囲への理解の求め方についても考えることができるようになる。
だから、医師の診察とカウンセリング、両軸が安心と支援、自立につながるのではないかと娘の経験から思っています。
ただ、診察を受けるためには、これまた「精神科」「心療内科」「メンタルクリニック」という、心を扱う医療になるとカウンセリングを受ける以上にハードルが上がることも事実です。
だから、のちに医療を受けることは頭に残し、まずカウンセリンで相談するのもいいのではないかと思います。
私は、大アリだと思います!
🌱 カウンセリングに迷っている方へ
私たちもはじめは不安でしたが、信頼できる人に出会えたことで前に進めました。
まずは、相談してみませんか?
👉 オンラインで相談できるカウンセリングはこちら
![]()

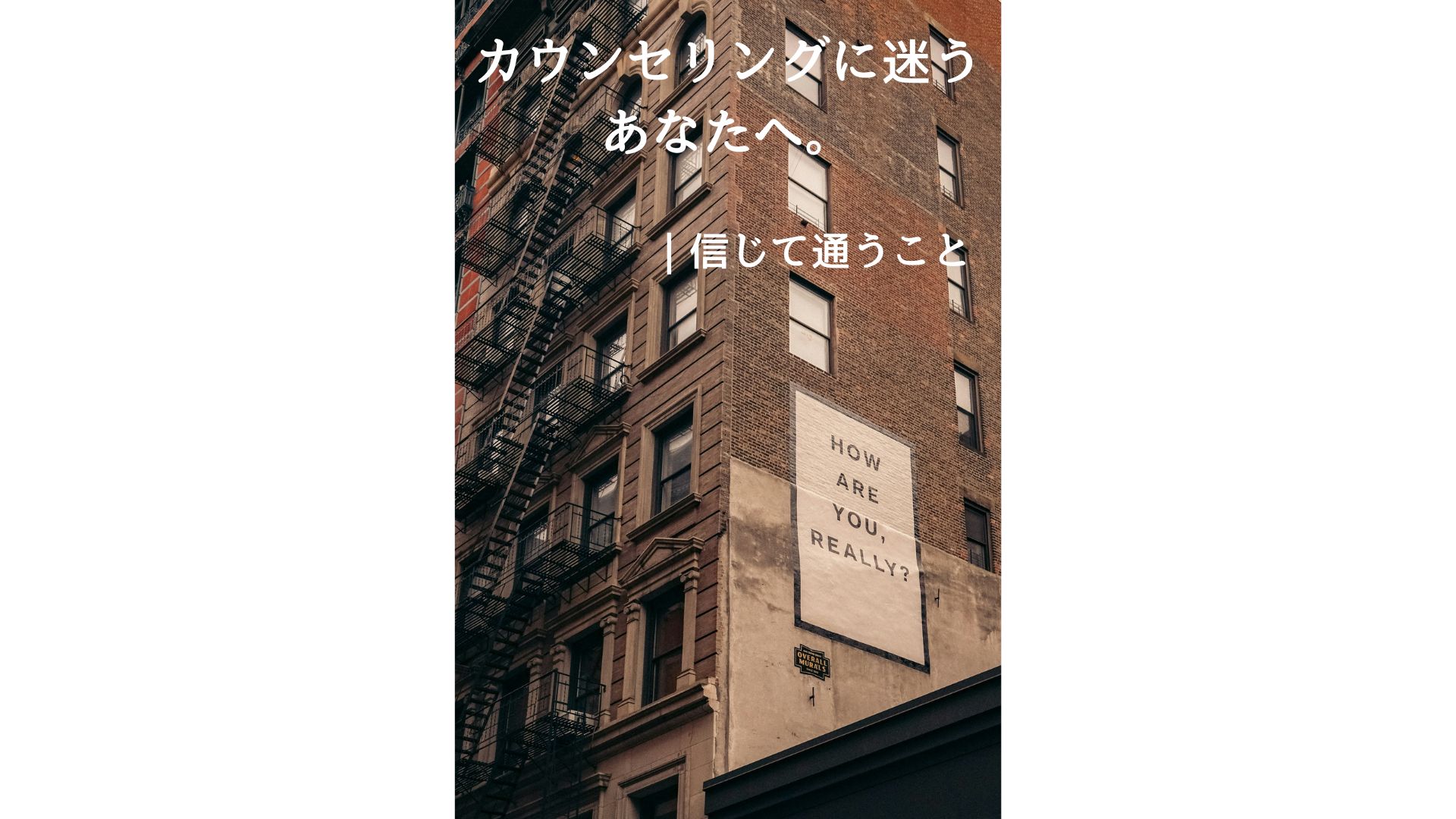



コメント