大学院での研究ができることを楽しみに、今年の4月に進学した娘が、わずか3ヶ月で休学することに。
実は、大学3年生のときにも一度休学していて、これが再びの休学です。
でも、私の受け止め方は、3年前とは少し違いました。
その背景には、ふたりの心理士さんの存在があります。
今回の記事では、
・私がカウンセリングを通して変わっていったこと
・母としての視点から、支援者としての視点へ移行したこと
・娘の気持ちに寄り添うまでの葛藤
についてお話しします。
突然の体調不良、その背景にあったもの
娘に、下痢と嘔吐の体調不良がみられ始めたのは、5月末ごろ。
6月に入るとさらに悪化し、普段から学校や授業を休むことを嫌う娘が、吐き気で通学途中に引き返したり、朝起きられなくなっていた。
心配して声をかけても「なんでもない」「話してもわからない」と、不機嫌に返事を返すだけ。
体調不良や学校、授業の欠席の報告は、私が外出や仕事中に届くLINEで知るだけ。
何が起きているのか、まったくわからなかったけど、この体調不良の原因が大学院であることは、だいたい想像できた。
そして、ある日、届いたLINE。

大学院辞める。
私には合わない、無理だわ。
明日、就職相談に行く。
あ〜〜〜、いつもゼロ⇨100の展開だ。
退学?休学?母の冷静な判断
あまりに一方的な報告に、
・何も聞いていないから、このままで退学は受け入れられない
・支援課に相談するとか、他の選択肢を探してからでも遅くないんじゃない?
かつての私なら、娘の発言に感情でぶつかっていた。
でも、今回は冷静に。火に油だとわかっていたから。
実際、娘も一般企業での就職には向いていないと自分でわかっていて、大学院に進んだという経緯がある。
「就活したい」と言うなら、一度やらせてみてもいいのかもしれない。
他者視点で自分を知るいい機会になるかもしれない。
そう考えて、無理に理由を聞いたり話しあったりせず、娘がどうしていくのかしばらく様子を見ることにした。
休学の決断と、母からの提案
その後も体調は悪化し、ついには39度台の高熱、激しい下痢と嘔吐。
食も細り、1日中ほとんど寝ているような日が続いた。
「退学」のLINEから1週間が過ぎても、自分からは何も話してこない。
もう娘の限界だと判断し、私から「休学」を提案した。
娘もすでに心を決めていたようで、「退学」は口に出さなくなり、「休学」で落ち着きました。
6月30日(月)、前期の休学願受付最終日。
私は仕事を休み、娘を車に乗せて大学へ。
休学願を提出しました。
娘の言葉から見えた「無理だったこと」
大学への道中、方向が決まって気持ちの落ち着いた娘は、ようやく口を開いてくれました。
体調不良の理由は、大きく2つ。
ひとつめ:流れについていけない

忙しいと覚悟はしていたけど、
それ以上に
・気遣い
・先回りの段取り
が必要で、その流れに乗れなかった。
うん、想像できる。
ASDの特性が強く出やすい部分。
「見えないこと」に気づいて動くことは、娘にとってとても大変なこと。
ギブアップしても無理もないかも。
ふたつめ:教授からの強い当たり

教授ふたりに、かなりキツく当たられる。
娘の言葉の受け取り方を考慮しても、話を6割に割り引いても、かなりきつい内容。
ゼミも研究室も楽しくて、頑張りたかった。
でも、両方重なってしまったことで、限界を超えたのだと。
村社会でもある研究所、教授という一人職業を生業にしている人たち。
大なり小なりあるでしょうが、学生をここまで追い込むのも考えもの。
実は、同じ理由だった大学3年生の休学
話しながら、ふと、大学3年生を休学した3年前のことを思い出した。
あの時も、話し合う間もなく娘の勢いのまま休学することになり、その後APD、ASDが診断されることになった。最後まではっきりした理由がわからないままだった。

対人関係も(問題が)あるにはあった。
でも、それよりも3年生でゼミが始まって、
やることも増えて、2年生までみたいに授業だけ
じゃなくなった事がしんどかった。
やはり今回と同じように「やることの変化」が大きかったとのこと。
と、いうことは、これを把握できていたら、今回のことは回避できたのかな?とも考える。
就活から見える成長
就活も、実際にやってみたとのこと。

今からでも仕事はあるって言われた。
でも、場所を変えても同じ事。
企業は私に向かないの。
だから、大学と研究を選んだし。
就活が違うことはわかってる。
そうか。
娘は、この場面において、「就職する」ということは、箱を変えるだけのことだとわかっている。そして、その箱に自分は合わないということも。
一度は逃げたかったのかもしれない。
頭でわかっていても心が・・・。
だけど、頭と心がまだ一致しないかもしれないけど、色々なことを経験して、自分分析ができるようになっている。
これまでのように衝動で動いて、後からまたそのことに落ち込む、と言う悪いスパイラルは減ったみたい。
娘の成長を感じた。
今の人間関係
そして、大学院の同級生や研究室の先輩など学生同士の人間関係は、

概ね、いい人が多い。
割と助けてくれるし、そんなに
嫌な人はいない。
心配していたので、それなら、良かった。
また戻る場所。
いよいよ、娘を待っている人たちに会えたと思いたい。
支援者視点を持つようになったきっかけ
3年前、娘がASDと診断されてからの私にとって長くて短い期間、娘の頭の中、気持ちの底を理解することに本当に苦労した。
私の感情もあるし、娘以外のふたりの息子のこともある。
でも、娘は苦しい。
それをどう理解すればいいのか。
ふたりの心理士さん
現在、私の思考の背景には、娘を支えてくれているふたりの心理士さんがいる。
一人は、娘の大学常駐の女性の心理士さん。
大学3年生の休学時点から2年半ほど、1〜2回/月のペースで娘はカウンセリングを受けていた。
本人とのカウンセリングが基本の中、安倍元首相の事件に動揺した娘の相談を電話でしたことをきっかけに、それ以降も自宅での娘の様子、出来事などについて2〜3度電話相談でアドバイスをいただいた。
その後、4年生の夏から心療内科通院を始め、そこでカウンセリングを受けるようになったので、現在は大学でのカウンセリングは受けていない。
でも、今回の件についても電話で即相談、対応してくださり、寄り添ったアドバイスをいただくことができた。
もう一人は、1年前から、娘が通い始めた心療内科の男性心理士さん。
特に、この心療内科の心理士さんは、娘が通院当初から心を開いている。
カウンセリングから帰る娘はいつも頭の中がまとまり、気持ちもほぐれて表情が穏やかになっている。
通院まもない頃は、家族カウンセリングとして、たくさんお話しを聞いていただいた。
現在は、私の「相談」という形で、不定期の主に電話でのカウンセリングを受けている。
私の心の背景にも目を向けるきっかけを与えてくれるから、おかげで娘との関係もずいぶんほぐれたように思う。
おふたりには感謝しかない。
「できないこと」を責めない視点へ|私の変化
母の感情は切り離す|分析
最近は言葉が口から出る前に、というより、娘と話す前、娘が話しかけてくる前に自然と頭のなかで何かを組み立てるようになっている。
そうしようと思って努力しているわけではなく、その思考と分析が働く。
それは、1年間のカウンセリングの賜物とも言える。
たとえば、今回の体調不良について。
今までの私なら、

体調不良の相談、もう少し違う形でしょ
とか、

そこまで体調不良ひどいなら、
24歳なんだから、自分で受診くらいしてよ
「心配してるのになんで?」や「また?」と、24歳の大学院生の娘に抱く、きっと母親として当たり前の感情がモリモリ怒りへと変化し、正面衝突で大炎上してきた。
でも、まず、
「私の娘はそれができないんだ」
と、思えるようになった。
誰かに相談することや自分の感情を吐き出すとか、協力者を作るとか・・・そんな、多くの人がやっていることができない。
だから、娘自身はしんどいんだ、と。
そして、「できない」と理解し
・今、娘は何に困っている?
・ここは言うべき?黙るべき?
・様子見ておける?止めないといけない?どんな止め方ができる?
娘がどう困っているのか、何がわからないのか?じゃあ、どう対応してあげれば、次に繋がるのか?と、考えられるようになった。
その中には「待ち」も「放置」も選択肢として出てくるようになった。
できないことやわからないことを、「なんで?」「どうして?」と言われることも窮屈だっただろう。
その窮屈さを、想像できるようにもなった。
男性心理士さんは、通院間もない頃の私を振り返り、
「よく(娘に)(感情の)爆弾投下してましたもんね(笑)」と笑う。
おかげで、終わりのない感情のぶつけ合いの言い争いは、今はなくなった。
娘に起きる出来事に対して、母の感情を切り離して考える。
母親というより、支援者という立場で娘を見つめる。
そんな見方をしている自分に、寂しさや母親として後ろめたさを感じた時もあったけど、最後に何も残らない徒労の言い争いがなくなり、娘との距離が以前のように近づいていることを感じれることができるので、これが正解なのかもしれない。
母として|感情
24歳の娘。
綺麗に着飾って、大学にバイトに私生活に、それはそれは忙しい時間を過ごしていると想像していた。
でも、それは私の想像。
娘時間
3年前、娘が21歳でASDと診断された当時、やっとうまくいかない原因が分かったのに、「なんでちゃんと向き合わないの?!」と娘に腹を立てていた頃があった。
でも、こうして、上手ではないかもしれないけど、ぶつかって立ち止まって、考えて選ぶことができている。
娘時間。
私とも他の誰とも違う時間のかけ方で、ゆっくりと少しづつ少しづつ、娘なりに自分に向き合い、選択し、進んでいる。
戻る場所
前期だけではなく、1年間の休学を申請した娘。
でも、1年後に戻るのは「娘が無理だったふたつのこと」が変わらず存在している場所。
大丈夫なの?の問いかけに娘は、

前期で経験して、少し分かった。
対策を考えて戻れると思う。
大学3年の復学がうまくいったから、
今回もなんとかできると思う。
『対策』!『うまくいった』!!
ある意味、成功体験?笑
でも、「戻りたい」と思っていることは嬉しい。
戻りたいし、戻らないといけない場所。
娘が“戻りたい”と思える場所があることが、まず何より大事なことなのだと思う。
私は、娘の専属の支援者として、これからも寄り添っていこう。

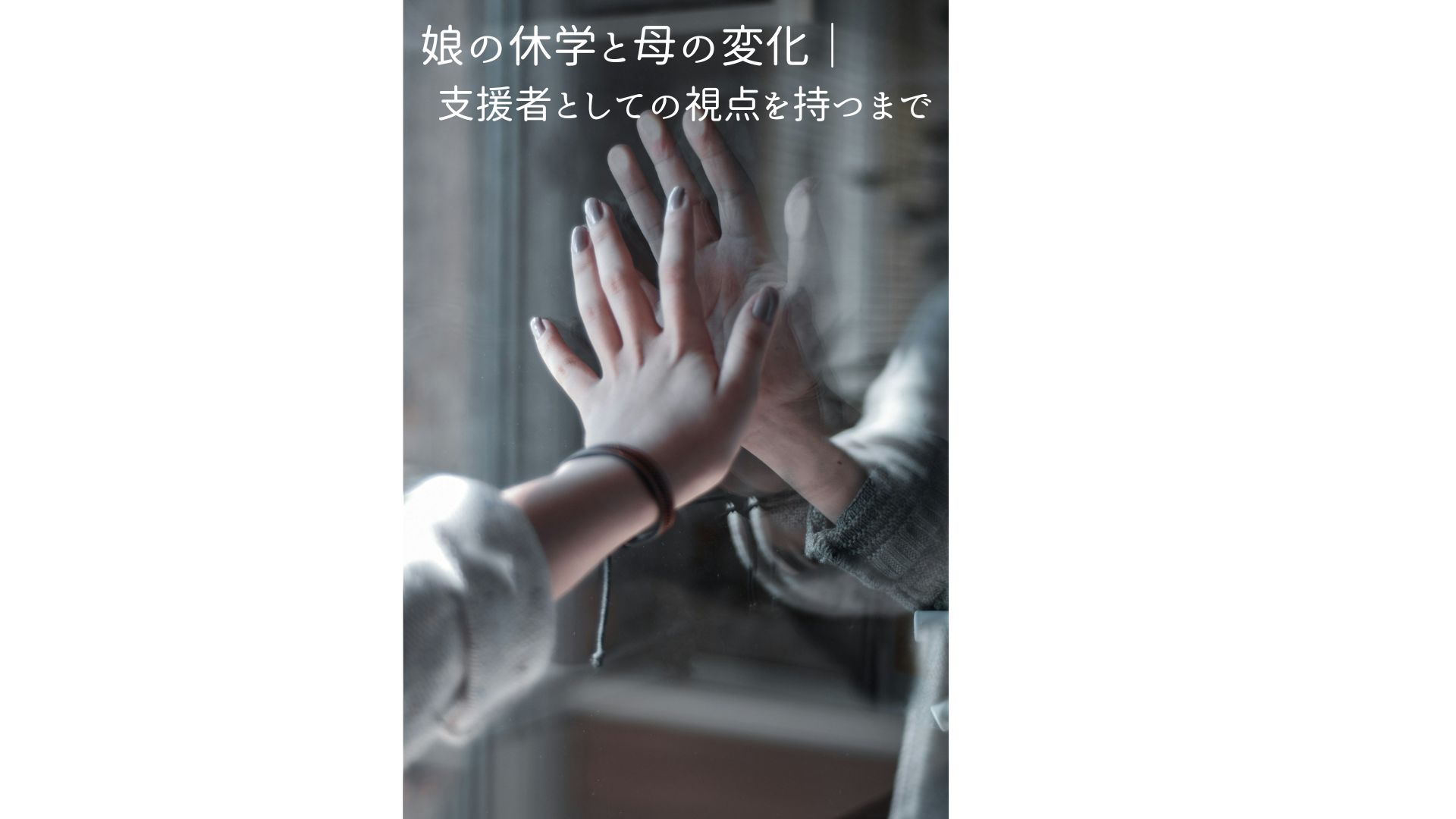


コメント